離婚協議書、公正証書の書式、ひな形の決定版!
公正証書を作れば、養育費や慰謝料の未払いが発生したら、強制執行により取り立てることができます。
「離婚協議書(公正証書)を自分たちで作りたい」
「ネットで見つけた書式・文例を使ったので、本当に文面が正しいかどうか不安」
「財産分与でローンの残っている不動産のことでもめている」
「年金分割をする際の書き方が知りたい」
「この文面で、将来どのような問題が起こるのか知りたい」
「専門家が作った見本を見ながら作りたい」
そんなお客様のご要望に、本マニュアルがお応えします。
豊富な文例と解説で、確実にご自身で離婚協議書を作ることができます。
しかも・・・
「マニュアルを見ながら自分たちで作ってみたけど、やっぱり専門家にお願いしよう」
という場合には、マニュアルの購入代金分を、当事務所への離婚協議書(公正証書)の作成報酬から差し引かせていただきます。
つまり、「やっぱり山本行政書士事務所にお願いしよう」という場合でも、マニュアルの購入代金で損をしてしまうことがありません。安心してご購入いただけます。
マニュアルの内容、公正証書の文例は、インターネット上で「離婚協議書 書き方」などのキーワードで検索すると表示されるサイトに掲載されている文例等とは違い、もっと踏み込んだ内容、1つ1つの条文に対する注意事項(それを書くことで、将来どのような問題が起こるのか等)まで記載しております。
また、マニュアルの記載通りにやってみて、どうしても不安な点、疑問点などございましたら、いつでも電話相談が無料で受けられます。
このマニュアルには、以下のような内容が収録されています。
|
「自分でできる離婚公正証書作成マニュアル」の内容 離婚協議書を作ることの意味、作らないとどうなるのか、公正証書にすることのメリットなどを説明しています。 離婚時に決めるべき「親権」、「養育費」、「慰謝料」、「財産分与」、「面接交渉」などについて、詳しく解説しています。 夫婦の合意がなければ公正証書はできません。そこで、相手方が作成に応じない場合の対処方法、交渉方法などを記載しています。 自分たちで作った離婚協議書をもとに、自分たちで公正証書にすることができます。しかし、これには危険な罠が潜んでいます。自分たちで公正証書にする際に、気をつけなければならない点を解説しています。 実際に、このマニュアルをどのように使ったらいいのか、離婚協議書の作成方法について解説しています。 一般的な形の条文について、1つ1つ解説をしています。 以上の6つの基本的な文例を、部分的ではなく、最初から最後まで省略せずに記載しています。これらのタイプに当てはまる離婚をされる方は、そのままお使いいただけます。 離婚協議書は、すでに離婚してしまっている場合でも作ることができます。 文例7は、そのような場合に使える文例です。 離婚協議書の最後に署名・押印をしますが、その際の注意事項と、ページ間の契印のやり方について解説しています。 養育費について、さらにいろいろな条件を付けたい場合の文例です。 (この文例は、そのまま書くには危険ですので、注意点や、さらなる改善方法を説明しています。) 慰謝料について、分割払いにする場合と、浮気相手に払わせる場合の文例です。 現金以外のものを財産分与する場合(特に不動産や車など)の文例です。 子供と月に何回会うかということ以外に、入学式や参観日への参加を認める場合などに使える文例です。 熟年離婚の方の場合、年金分割があるかもしれません。そこで、離婚協議書に年金分割のことを入れたい場合の文例です。 「包括的精算条項」とは、「この書面に書いてあること以外は、今後一切、お互いに何の請求もしません(できません)」ということを宣言する文章です。 この一文を入れるか入れないかで、将来、どのようなメリット・デメリットがあるのかを解説しています。 自分たちで無事に離婚協議書を完成させることができたら、その後、公証役場へ行くわけですが、公証役場に対して、どのようにコンタクトを取ればいいのか、また公証役場へ行くときの持ち物などを解説しています。 |
上記のような内容が収録されています。
マニュアルをご購入後、「やっぱり山本行政書士事務所へお願いしよう」という場合には、マニュアルの購入代金を、当事務所への離婚協議書の作成報酬から差し引かせていただきます。
つまり、マニュアルの購入代金は無駄にはなりません。安心してご購入ください。
また、マニュアル通りに離婚協議書を作成してみて、「やっぱり不安」ということがございましたら、いつでも電話相談を無料で受けることができます。
マニュアルの価格は、7,800円です。(冊子版は8,800円)
さらに、失敗しない「離婚届」の記入方法や、離婚後に家庭裁判所で行う「子の氏の変更許可申立」手続をご自分でできるように解説したマニュアルをオプション(+2,000円)でお付けしております。
オプションでお付けするマニュアルには、以下のような内容が記載されています。
| オプション「離婚後の手続きマニュアル」の内容 離婚届の書き方を、よくある3つのパターンに分けて、記載例を写真とともに掲載しています。 1.子供がおらず、離婚後に奥様が婚姻前の父母の戸籍に戻る場合の記入例 2.子供がいて、離婚後に奥様と子供で新しい戸籍を作る場合の記入例 3.離婚しても、奥様が旧姓に戻らない場合の記入例 何度も役所へ足を運ばなくてもいいように、一度で受理されるためのポイントです。 離婚しても、奥様が苗字を旧姓に戻さない場合に書かなければならない「離婚の際に称していた氏を称する届」の書き方を、記載例の写真とともに解説しています。 また、この手続をする場合の注意事項、デメリット等についても解説しています。 離婚後、何もしないでいると、子供だけが夫の戸籍に残ってしまいます。子供を母親と同じ戸籍にするには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続と、役所への「入籍届」の提出が必要になります。 奥様が一人で家庭裁判所へ行って、手続で迷わないように、全てを一度で済ませるための準備・必要書類・申立書類の記入方法などを解説しています。詳細な記載例が掲載してあります。 (全26ページ) さらに、「離婚後にしなければならない手続き一覧チェックシート」をお付けします。 離婚後に必要となる児童手当の申請窓口やパスポートや国民健康保険の手続等を、どこへ、何を持っていけばいいかの一覧表です。手続き漏れがあると大変ですから、ぜひご活用ください。 |
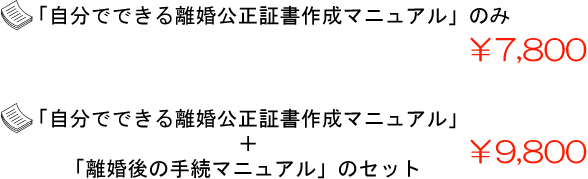
購入方法は以下の2通りです。
→ このページ下にあるお申込みフォームを利用してください。
お申込み後に、クレジットカード決済できる決済画面のURLをメールにてお知らせします。
お申込みは、以下のお申し込みフォームに必要事項を入力して送信してください。
お申込みフォームがうまく作動しない場合は、メールにてお申込みください。
お申込みフォームがうまく作動しない場合は、メールにてお申込みください。